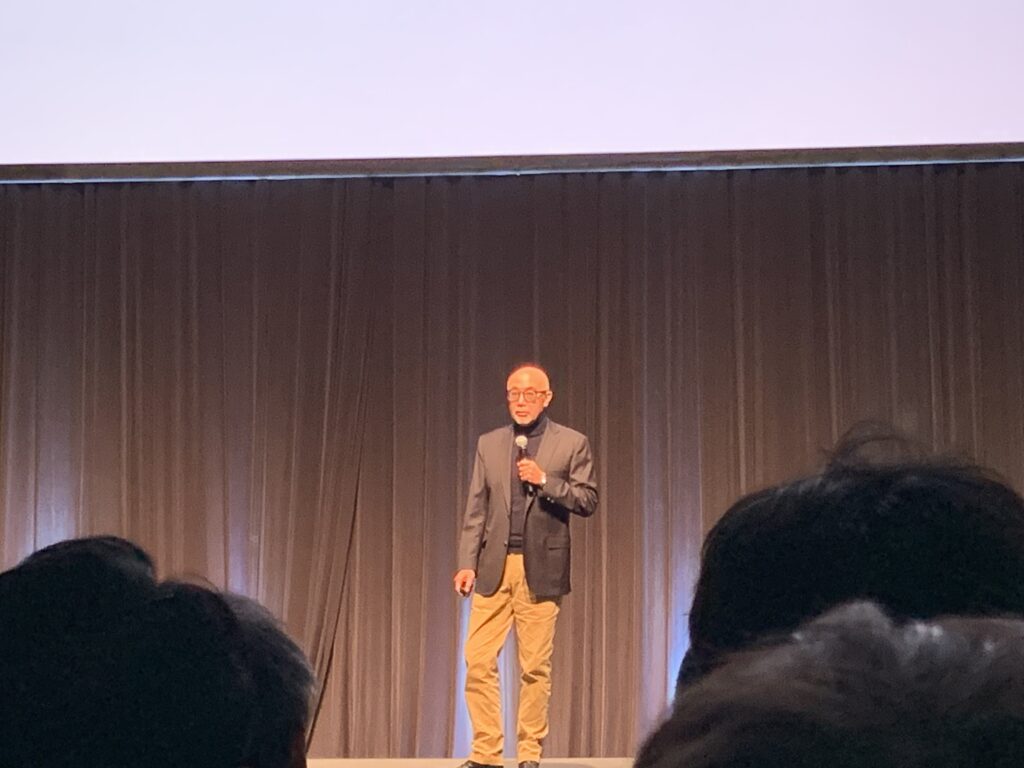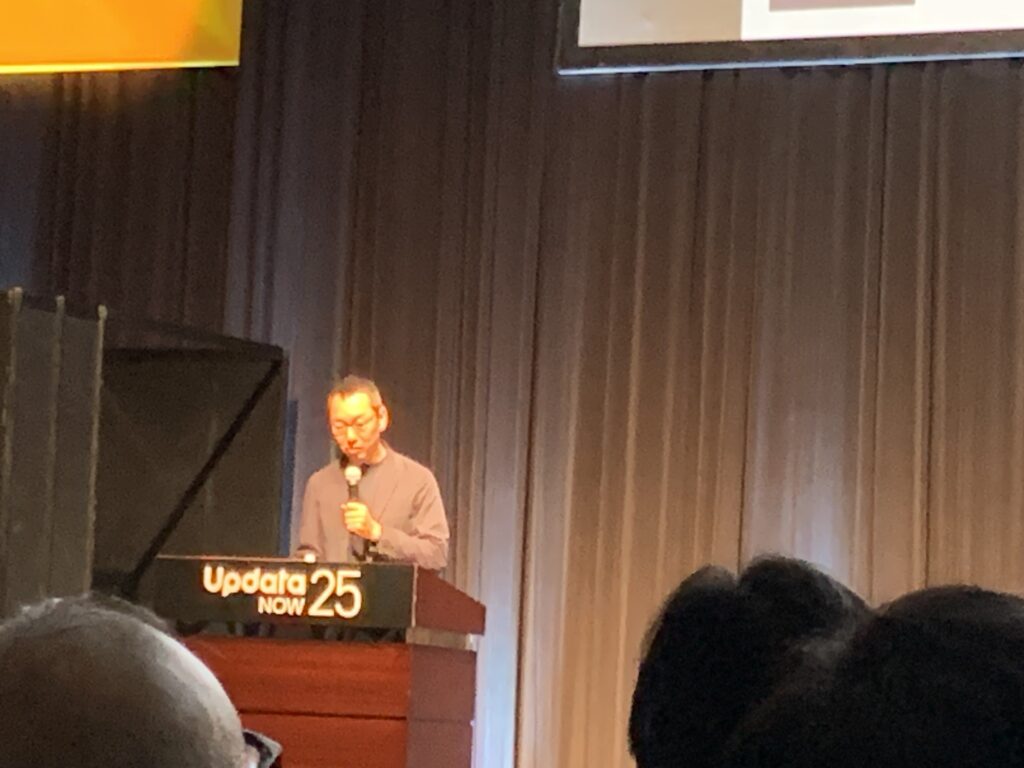1. 楠木健氏に学ぶ、競合を「その気にさせない」痺れる戦略
楠木先生のテーマは「痺れる戦略」です。
多くの企業がブルーオーシャン市場を開拓しても、成功すればすぐに競合が参入し、あっという間にレッドオーシャンと化してしまう。先生が提唱する「痺れる戦略」の神髄は、この模倣競争から抜け出し、競合に「そもそも真似しよう」と思わせない、「その気にさせない」ことにあります。
その戦略は、一見すると「なぜそんな非効率なことをするのか?」と首をかしげるような打ち手にこそ宿ります。短期的・部分的に見れば非効率でも、長期的・全体的に見れば他社を圧倒する参入障壁となるのです。
その要諦の一つが、「徹底的に手間を肩代わりする」ことです。例えば、ワークマンやユニクロは、高機能な製品を低コストで提供するために、サプライチェーンや販売手法に膨大な「手間」をかけながら、それを低コストで実現する「仕組み」を磨き上げてきました。この「手間を圧倒的な低コストで実現する」ことが、他社を「その気にさせない」強力な壁となっています。
もちろん、それだけでは顧客の変化についていけません。徹底した「ユーザーイン」の目線で顧客の声に耳を傾け、商品を開発する独自の仕組みをつくっています。高機能とデザイン性を高価格で販売するブランディングが多い中、顧客目線でムダを省き、本当に必要な機能だけを磨き上げていく「シンプルさ」こそ、日本企業が世界で戦う上での大きな強みだと感じます。
あえて非効率な「手間」に未来への投資として向き合う。この視点の転換と「意味づけ」の重要性は、私自身のコンサルティング業務においても大変重要な示唆であり、深く掘り下げていきたいテーマでした。
2. 山口周氏に学ぶ、人生のポートフォリオ思考
山口周先生は、『人生の経営戦略』の視点から現代のキャリア戦略を語りました。人生100年時代を迎え、AIの進化も相まって、一つの仕事に専念するのではなく、仕事やスキルを「ポートフォリオ」として多角的に運用することが不可欠になります。長寿化を単なる「不安」ではなく「挑戦できる時間が増えた」と前向きに捉え、戦略的に生きることの重要性を再認識しました。